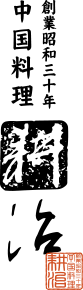歴史 其の八ー1

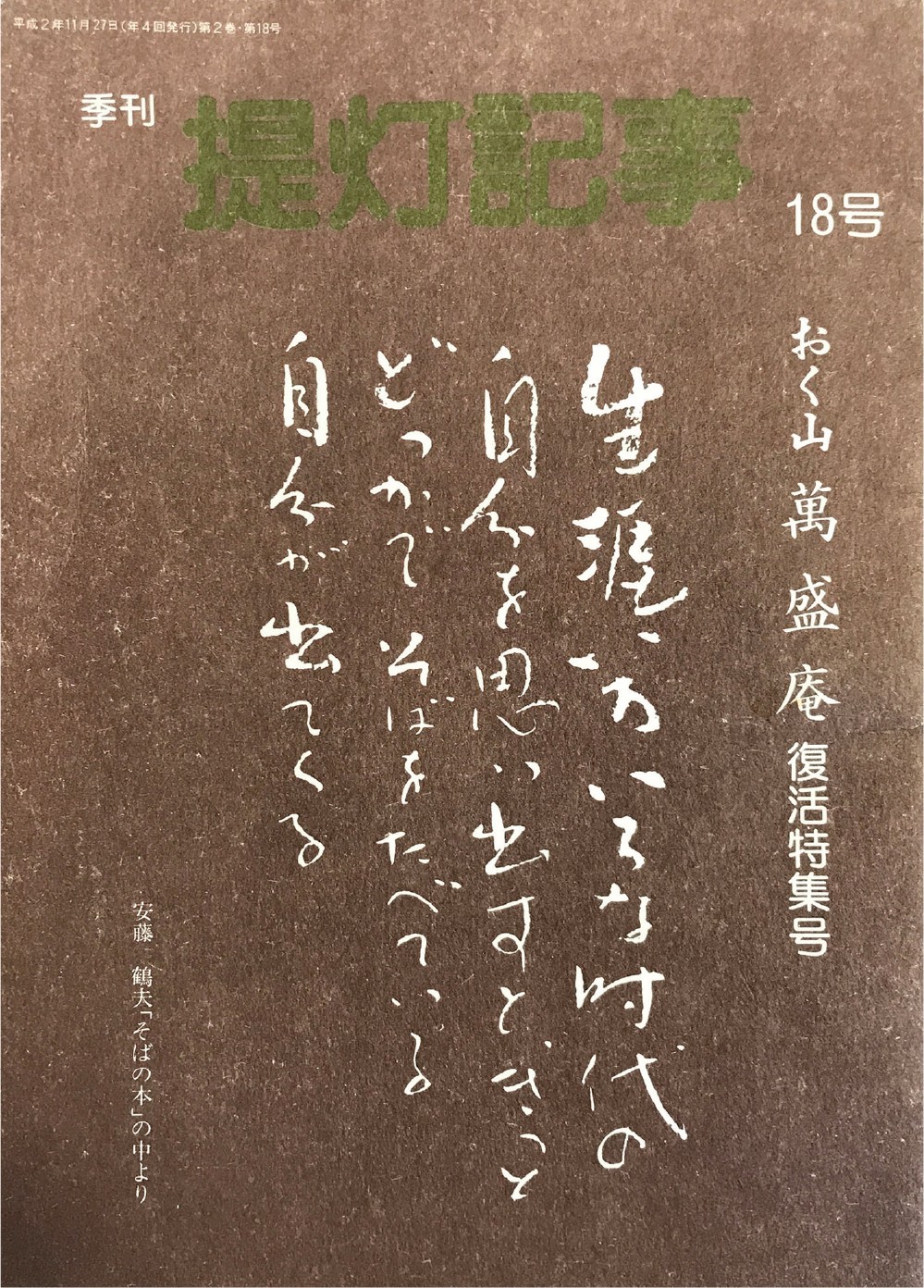
文化人や著名人にも
ご寄稿頂いた季刊誌
「提灯記事」
「最後のそば」 永 六輔この夏、点滴で生命をつないでいた父が、九十才という年齢もあって、最後は自宅でという形で退院した。ところが自宅に帰ったら「そばが喰べたい」と言い出し、せめて、その香りでもと、僕が更科から運んだら、点滴だけだったのに、そばは喰べる、しかも元気になる。三日続けてそばの出前をしたが、そんなに元気ならもう一度入院してと・・・。病院に戻って、今度は帰れなかった。アッというまの大往生だった。父は最後に好きなそばを喰べに家へ帰って来たのだった。僕も、最後に好きなものがちゃんと喰べられるかどうか。四十九日、納骨。そして秋。父を想うと、僕も父のように、最後に好きなものが喰べられるかである。喰べたいなァと思いながら死ぬのは大往生ではあるまい。といって。「うまかった!」と死ぬのは、これは難しいことだと気がついた。喰べたいものを目の前にしながら、喰べる元気がなくて死ぬのも辛い。例えば東京の病院で、小倉の耕治のラーメンが喰べたいと思ったとする。土産用もいいけど、あの店の、あのカウンターで熱いのをと思ったら悲劇である。そんなことを考えると父は、喰い気を満足させての大往生。食欲は最後まである欲だから、余程上手に臨終を迎えないことには、父のようにはいかない。最後が病院の食事というのだけは避けようと考えている内に、正月などに餅で窒息死する老人がうらやましいと思えるようになった。元気な時にどんなうまいものを喰べてもあまり意味がない、問題は「最後の晩餐」だ。・・・・・と考えてもこればかりは自信がない。そこで、やっぱり、元気な間にうまいものを喰っておこうと諦めることになる。長い間「お父さんは立派なのに、あなたは・・・・・」と言われ続けてきた。最後まで立派じゃとても父を追い越して逆転サヨナラも出来ない。せめて僕は喰べたいものを連呼して、周囲のものを右往左往させてやろう。そうすれば、せめてお墓に備えてくれる。こんな話を書いている内に思い出したことがある。よく酒飲みの墓に酒をかけているが、あれは墓石を痛めるのだそうだ。墓には水をかけ、酒は自分で飲んで故人を偲ぶのが一番、と石屋サンが言っていた。さて、というわけで僕はこれからそばを喰う度に父を思い出すことになるだろう。そば好きで良かったと思う、今日この頃である。
※平成2年11月27日(第18号)掲載